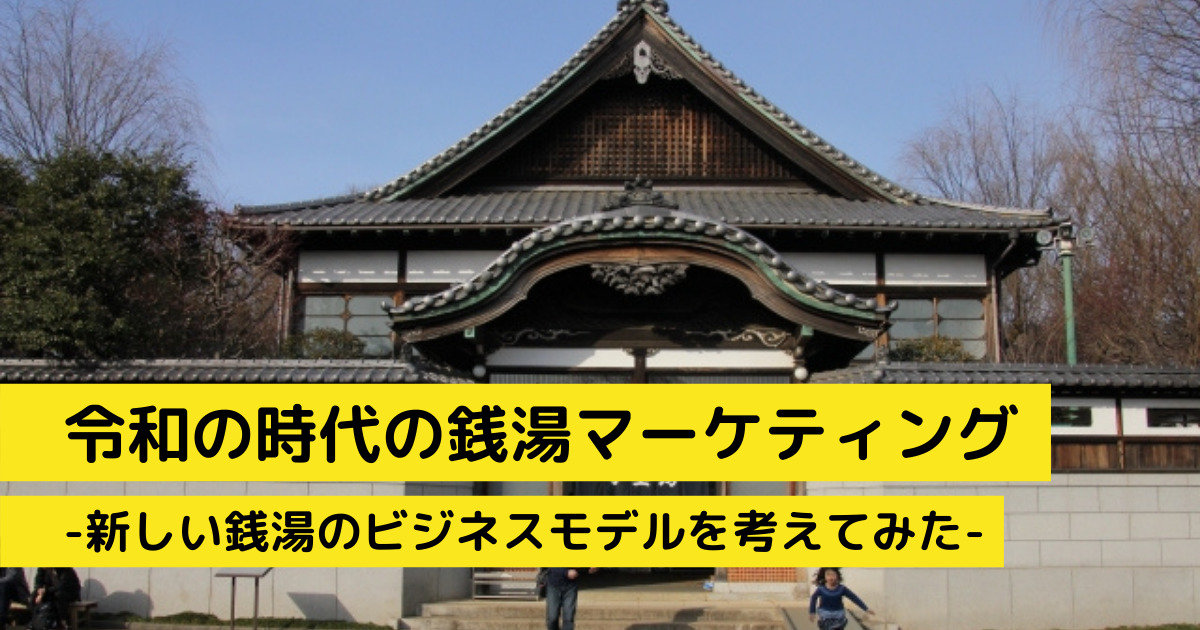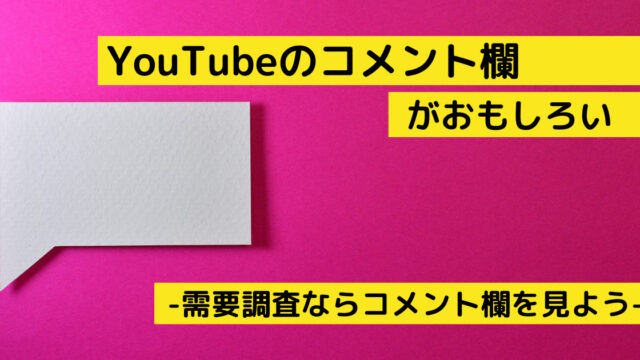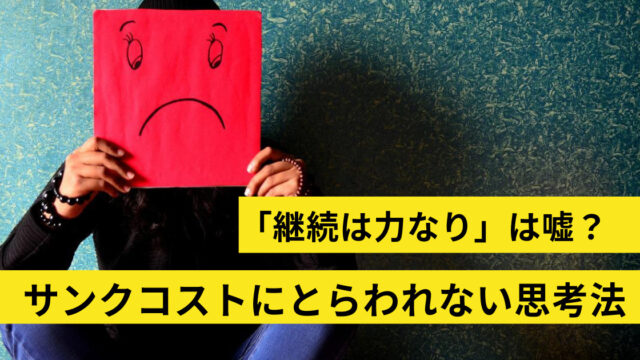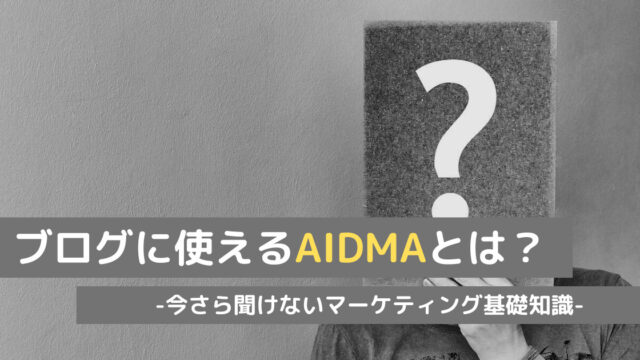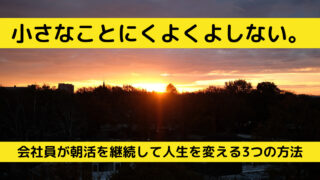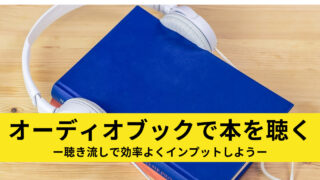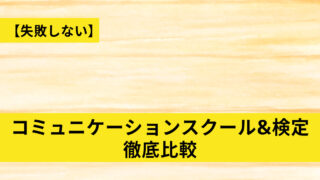「今日は疲れたから銭湯でも行こうかな」
「銭湯上がりは牛乳に限るね!」
昔ながらの日本を思い出させてくれる銭湯。
日本人なら一度は行ったことのある方も多くいらっしゃると思います。
近年はスーパー銭湯という形で、飲食や飲酒、マッサージ、岩盤浴、漫画など、入浴以外の様々なサービスも充実しています。
そんな銭湯は、実は様々なマーケティング施策を取りやすい業種なのです。
今回は、銭湯というビジネスモデルにどのようなマーケティング施策が打てるかをまとめてみました。
結論からいうと「生活必需品×箱モノは最強」ということ。
鍵となるとはプッシュ型のアプローチです。
それでは詳しく見ていきましょう!

銭湯が減っている!?
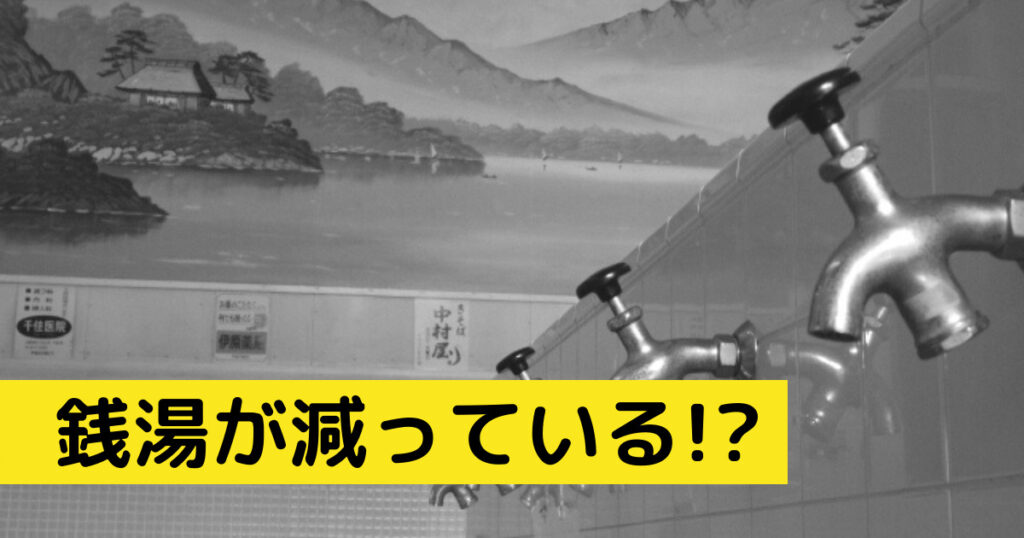
実は日本全国の銭湯が急速かつ大幅に減ってます。
1968年の全国17,999件から減少が続き、2022年は1,865件と実に89.6%減。
その理由は「廃業」や「転業」が大半を占めます。
たとえば2021年度の銭湯の倒産は1件にとどまっています。
もともと、自宅に風呂がなかった時代、公衆衛生を保つために開かれたのが銭湯です。
そのため銭湯は「公衆衛生法」により入浴料金などを厳格に管理されています。
ちなみに、スーパー銭湯や健康ランドは、法律上の銭湯に該当しません。
法律による入浴料の管理。
燃料や電気代の高騰による固定費の高騰。
一家に1風呂が当たり前の時代。
主にこの3つの原因により、約90%の銭湯が現代の社会から姿を消しました。
過去の銭湯ビジネスモデル

公衆衛生のためにその数を増やしてきた銭湯。
時代の流れによって、その数が淘汰されてきました。
そもそも銭湯とは次のような場所です。
①体を清潔にする場所
②リラックス・リフレッシュする場所
③コミュニケーションを取る場所
従来の銭湯は「①体を清潔にする」ことを重要視してきました。
入浴は毎日の生活に取り入れられることです。
日本人にとって入浴とは、食事や睡眠と同等レベルで必要とされていること。
そのため銭湯が繁栄してきたのです。
しかし「①体を清潔にする」は、今やほとんど自宅でできてしまいます。
これからの時代は、銭湯というビジネスをどのように変化させていく必要があるのでしょうか。
そこで鍵になってくるのは②③となります。
これからの銭湯ビジネスモデル

「体を清潔にする」ことは、自宅でできてしまう現代。
銭湯のビジネスモデルで鍵になるのは
②リラックス・リフレッシュ
③コミュニケーション
でしょう。
②リラックス・リフレッシュする場所
銭湯に入浴は欠かせません。
体を清潔にするという意味での入浴ではなく、いそがしい現代人の「心身を休める場所」としての機能が、強い効果を発揮します。
たとえば、職場のデスク上にスマホが置いてあり、スマホが視界に入るだけで作業効率が50%減るという研究もあります。
入浴するためには裸になり、身にまとうものが一切ありません。
そのため余計なことに思考を引っ張られることが無くなります。
余計な通知に心を左右されることなく、ゆっくり自分の時間を取ることで、リラックス・リフレッシュできるでしょう。
銭湯はこの効果を最大限に発揮できる貴重な場所なのです。
また、最近は「サ活」というサウナ入浴が流行っています。
サウナがある銭湯が人気なのは、人々がリラックス・リフレッシュを求めているからでしょう。
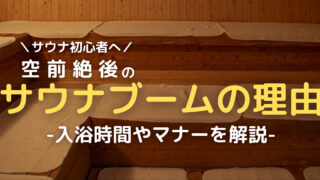
③コミュニケーションを取る場所
銭湯のもう1つの重要な機能として「交流の場」が挙げられます。
定期的・継続的に通っているとなんとなく顔馴染みができます。
声はかけずとも、いつも顔を合わせる人の存在が、心に安らぎを与えてくれます。
無言であってもいいのです。
料金を支払い、入浴し、他者が話していることに耳を傾ける。
(コロナ禍では黙浴が推奨されています)
入浴後にロビーで牛乳を飲んで少しの間休憩を入れる。
コミュニケーションは、言語的と非言語的に分けられます。
また、言語的コミュニケーションで使う脳と、非言語的コミュニケーションで使う脳も異なります。
そして非言語的コミュニケーションで使う脳の面積の方が、はるかに大きな比率を占めます。
人間が言葉を使い始めたのは、長い人類の歴史の中から見ると、ほんのわずか。
銭湯に無言で入ったとしても、非言語的なコミュニケーションをとっているのです。
この「交流の場」としての機能が、現代の銭湯には求められているのです。
もちろん言葉を使ってコミュニケーションを取る方にとっても有益な場所であることは、いうまでもありません。
【結論】これからの銭湯はプッシュ型の施策が鍵
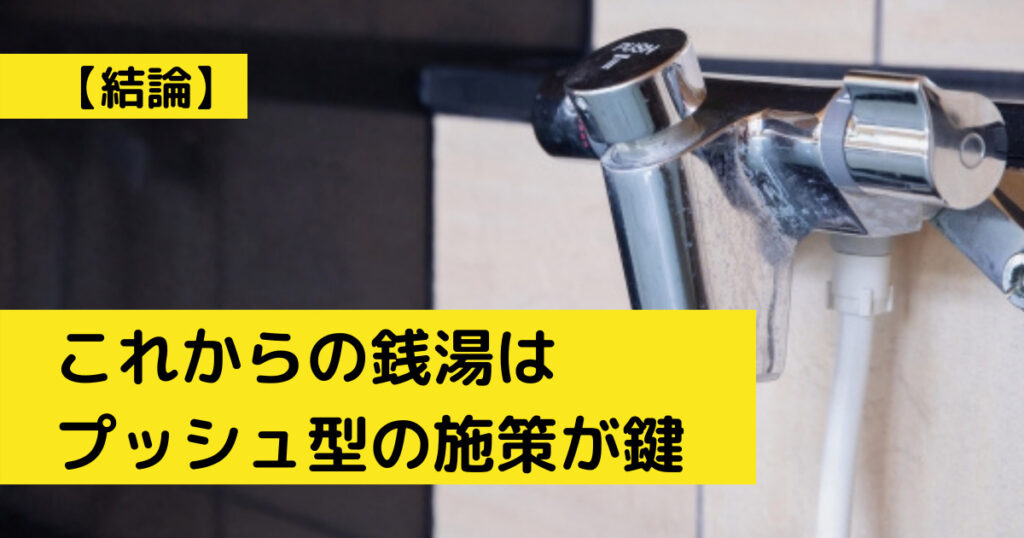 銭湯は「施設・設備」というハード面での資産を持っています。
銭湯は「施設・設備」というハード面での資産を持っています。
この資産を活かし、入浴目的のためにきた来場者に、下記のような「プル型」のマーケティング施策ができます。
✔️飲料の販売
✔️酒類の販売
✔️マッサージの提供
✔️軽食・アイスなどの販売
✔️ヨガなどの運動イベントの開催
✔️公開講座などの学習イベントの開催
✔️カフェ・居酒屋の併設運営
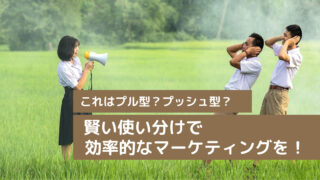
入浴料は法律で定められています。
ですので入浴料以外の収益方法を強化することで、収益アップは十分に見込めます。
①体を清潔にする場所
②リラックス・リフレッシュする場所
③コミュニケーションを取る場所
という銭湯最大の魅力を特化させることが、これからの銭湯の生き残り戦略でしょう。
会社員は銭湯に癒されつつ、これから銭湯がどのようなビジネスモデルをブレイクスルーさせていくか、注目していきましょう!